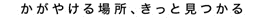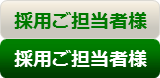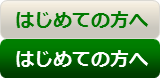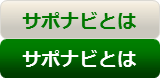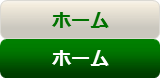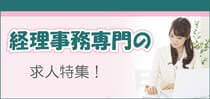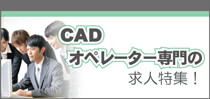和包丁の生まれた歴史

日本に製鉄の技術が伝わったのが、5世紀頃といわれています。いわゆる古墳時代なのですが、世界最大の前方後円墳「仁徳天皇陵(大阪府堺市)」の建設の際、全国から鍛冶職人を一ヵ所に集めて、建設に必要な鋤(スキ)や鍬(クワ)といった道具を、打刃技術で作らせていたというから驚きです。
安土桃山時代より、盛んにおこなわれてきた南蛮貿易は、日本にさまざまなものをもたらしました。中でも、ポルトガルから港町堺に伝わったタバコは、人々の間で徐々に広まっていき、タバコの栽培も盛んにおこなわれるようになりました。タバコ葉は、収穫して乾燥させてから細かく髪の毛ほどの幅に刻んでいくのですが、堺の鍛冶職人達が作った、タバコ包丁の切れ味が非常に良いと評判になり、瞬く間に世間にその名を轟かせました。これが堺包丁の起源となります。江戸時代にはこのことがきっかけで、他の地域の刃物とは別格の扱いを受け、幕府から「堺極」の刻印を賜り、流通は専売扱いになりました。
* 南蛮貿易で渡来したモノ *
 新潟県(越後)、岐阜県(美濃)、福井県(越前)、岡山県(備前)、京都府(山城)、奈良県(大和)など、日本国内において、刃物を特産品とした地域はいくつもありますが、いずれの地域もかつては日本刀の生産地として、卓越した技術を誇り、名だたる名刀を生み出してきた地域です。
新潟県(越後)、岐阜県(美濃)、福井県(越前)、岡山県(備前)、京都府(山城)、奈良県(大和)など、日本国内において、刃物を特産品とした地域はいくつもありますが、いずれの地域もかつては日本刀の生産地として、卓越した技術を誇り、名だたる名刀を生み出してきた地域です。

しかし、時代が戦のない泰平の世(江戸時代)に移り、戦道具である日本刀の需要が減少していくと、各地でその高い技術を駆使した様々な刃物が生み出されました。中でも包丁への技術の応用が目覚ましく、現在日本で使われている和包丁は、この時代に既に完成しています。菜切り包丁、薄刃包丁、出刃包丁、刺身包丁(関西では柳刃または正夫、関東では蛸引)など。
日本の食文化においては、明治の文明開化までは変わらず魚と野菜が中心だったため、それらの食材に応じた専門的な和包丁が、数多く生み出されました。
日本の食文化においては、明治の文明開化までは変わらず魚と野菜が中心だったため、それらの食材に応じた専門的な和包丁が、数多く生み出されました。
明治の文明開化によって日本に入ってきた西洋文化は、食文化にも大きな変化をもたらします。それまであまり食べなかった肉を食すようになったのです。西洋の料理では肉を多用します。食材や調理方法と共に、肉をさばく牛刀も入ってきました。日本の文化では食材を引いて切るため、体重をかけて押し切るタイプの牛刀は、日本人にはとても扱いにくかったのです。その様な時代の中で、日本人が使いやすく、肉・魚・野菜といった和洋折衷どちらの食材にも使える包丁はないものか?そんなニーズに応えて生まれたのが、「三徳包丁(万能包丁、文化包丁とも)」です。普段からなじみある菜切り包丁のような直線的な刃物に、牛刀のもつカーブの切っ先を併せ持つことで、今まで食材に合わせて包丁を換えていたのが、これさえあれば大抵の料理ができるようになり、一気に広まっていきました。現代でも包丁を1本持つなら出刃包丁でも菜切り包丁でもなく、三徳包丁が一般的ですね。
包丁図鑑

| 和 包 丁 |
 菜切り包丁(両刃※諸刃ともいう) 菜切り包丁(両刃※諸刃ともいう)
 出刃包丁(片刃) 出刃包丁(片刃)
 柳刃包丁(片刃) 柳刃包丁(片刃)
その他: 薄刃包丁(片刃)、蛸引き包丁(片刃)
|
|---|
| 洋 包 丁 |
 牛刃(両刃) 牛刃(両刃)
 ペティナイフ ペティナイフ
 三徳 三徳※戦後の食文化の洋風化に伴い、 日本で考案された洋包丁 |
|---|
| 特 殊 包 丁 |
これらの包丁以外に、より専門的に特化した包丁
骨スキ 筋キリ 洋出刃 ふぐ引 身おろし出刃 寿司切 麺切り包丁
鰻さき包丁 鱧しめ |
|---|
包丁の持ち方・切り方・動かし方
包丁を使う際は、正しい姿勢をとることで怪我の予防につながり、効率もUPします。しかし、良い姿勢は自然と身につくものではなく、日頃からの心がけが大切です。変なクセがつく前に、ぜひ正しい姿勢を知って心がけましよう。
調理台に並行して置いてあるまな板にむかって肩幅に立ち、包丁を握る側の足を自然に半歩後ろにさげて、こころもち外側に腰をひねる。体重は両足に均等にのせて、上体を支える。調理台に寄りかかって切ってはいけません。

素材は、まな板と平行に置きます。
※当然、包丁はまな板に直角に交差して切ります。
※当然、包丁はまな板に直角に交差して切ります。

握 り 型
親指と人差し指で刃元の中央をしっかりと握り、残りの3本指で柄を握ります。
切る食材に刃をあてがって、スーッと向こうへ押し出
切る食材に刃をあてがって、スーッと向こうへ押し出

すように切ることが多い。
指 さ し 型
より繊細な作用をする場合の握り方です。人差し指を刃の峰(みね)に立てて、切る力を調整しながら、細かい包丁さばきを行います。

パンなどの柔らかいものや、すべりやすいものを手前に引くように切ることが多い。
魚 ・ 肉 ・・・・・・・・ 引 き 切 り
肉や魚のうま味は細胞の中にあるので、なるべく身を崩さないように切ることが望ましいため、力をかけずに切れる引き切りがベストです。

野 菜 ・・・・・・・・ 押 し 切 り
野菜の繊維は硬くて粗いため、押し切りの方が強い力を加えることができて切りやすいです。

基 本 の 切 り 方
 1.輪切り
1.輪切り
 2.半月切り
2.半月切り
 3.いちょう切り
3.いちょう切り
 4.小口切り
4.小口切り
 5.ななめ切り
5.ななめ切り
 6.乱切り
6.乱切り
 7.ぶつ切り
7.ぶつ切り
 8.せん切り
8.せん切り
 9.千六本
9.千六本
 10.拍子切り
10.拍子切り
 11.短冊切り
11.短冊切り
 12.さいの目切り
12.さいの目切り
 13.あられ切り
13.あられ切り
 14.みじん切り
14.みじん切り
 15.面取り
15.面取り
 16.くし切り
16.くし切り
 17.針切り
17.針切り
 18.白髪ネギ
18.白髪ネギ
 19.ささがき
19.ささがき
 20.桂むき
20.桂むき
 21.真空切り
21.真空切り
特 殊 な 切 り 方 ・・・・・・・・ 飾 り 切 ・ あ し ら い
 1. 花形切り
1. 花形切り
 2.矢車切り
2.矢車切り
 3.手綱こんにゃく
3.手綱こんにゃく
 4.菊花切り
4.菊花切り
 5.末広切り
5.末広切り
 6.切り違いきゅうり
6.切り違いきゅうり
 7.花切りトマト
7.花切りトマト
さ ま ざ ま な カ ッ ト フ ル ー ツ
ペティナイフで、フルーツを食べやすく、美しくカットすることで、食事シーンに彩りを添えることができます。



フ ル ー ツ ア ー ト
美しく、食べやすくするだけのカット技術にアート要素を加え、フルーツの葉や皮など通常捨ててしまう部分やB級品をも利用し、立体かつ美しく見せることによりフルーツの付加価値を高めるために考案された技法です。
よく切れる包丁があるからこそ生み出された芸術ではないでしょうか。

パパイヤ・スイカ・マンゴー・
ドラゴンフルーツなどの南国
フルーツを使ったアート作品
ドラゴンフルーツなどの南国
フルーツを使ったアート作品

スイカを器に鮮やかな
フルーツの盛り合わせ
フルーツの盛り合わせ

フルーツで作った
リースのサラダ
リースのサラダ

アップルローズ

スイカのバラと花かご
関連する求人特集
都道府県から求人をさがす
職種から求人をさがす